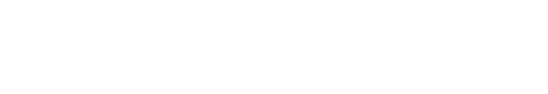- > 歯周病とは
- > 当院の歯周病治療について
- > 治療の流れ
歯周病とは
歯周病は細菌(歯周病菌)の感染によって引き起こされる炎症性疾患で、実に日本人の成人の80%が罹っているといわれています。
歯と歯の境目(歯肉溝)の掃除がきちんと行き届かない状態でいると、そこに食べかすが残り、歯垢になって停滞します。歯垢はやがて細菌の棲み家となる歯石に変化し、その細菌によって歯茎に炎症が起きていくのが歯周病のメカニズムです。

歯周病は細菌(歯周病菌)の感染によって引き起こされる炎症性疾患で、実に日本人の成人の80%が罹っているといわれています。
歯と歯の境目(歯肉溝)の掃除がきちんと行き届かない状態でいると、そこに食べかすが残り、歯垢になって停滞します。歯垢はやがて細菌の棲み家となる歯石に変化し、その細菌によって歯茎に炎症が起きていくのが歯周病のメカニズムです。
歯周病の症状
歯周病に罹っていても、初期の段階では痛みもなく、ほとんど自覚症状はありません。しかし、歯周病が進行していくと、歯茎が腫れて膿が出たり、歯を支える歯槽骨が溶けて歯がグラグラしたり、最後には歯を抜かなくてはならない状態にまでなってしまいます。
「歯を磨いていて歯肉から頻繁に出血する」「最近口臭が気になる」「昔に比べて歯が長くなった」「出っ歯になった気がする」「なんとなく噛みにくい」など、「おかしいな?」と感じたときには、すでに歯周病が進行している恐れがあります。このような症状を感じたときは、早めに歯科医に相談するようにしましょう。
歯周病と全身疾患
歯周病は放置しておくと全身に悪影響を及ぼすことが近年の研究で明らかになり、心臓や血管系の疾患、糖尿病、低体重児出産、また近年では認知症との関連性も指摘されています。痛みがなく、放置してしまいがちな歯周病ですが、少しでも気になる症状があるときには、早めの治療を心がけましょう。
当院の歯周病治療について

特に「自覚症状がない」という方でも、実際には歯周病に罹患されているケースがほとんどです。そこで当院では、ブラッシング指導や歯石の除去はもちろん、患者さまの状態に合わせた治療で「自分でブラッシングができるようになる」状態へと改善をめざします。
また、当院では医科との強い連携を生かし、特に歯周病との関連が深いといわれる糖尿病の方にも効率的な治療を提供しています。隣接する医科で糖尿病を治療しながら、当院で歯周病を治療することで、歯や歯茎の状態はもちろん、健康状態の改善にもつながるお手伝いができると考えています。
治療の流れ
歯周病の治療は、その進行度によって内容も治療も期間も変わってきます。そのため、まずはレントゲンや歯周組織検査、歯周ポケットの深さを測るといった検査で患者さまの状態を確認。その結果をもとに治療を選択していきます。
また、一度歯周病にかかった場合、治療をして症状が改善したからといって「治療終了」ではありません。よい状態を保つためにも、正しいブラッシング、定期的なクリーリングを「習慣」として継続するようにしましょう。
- 1軽度の場合
- 軽い出血や軽度の腫れが見られるといった軽度の歯周病の場合は、歯周病の原因となる歯垢と歯石を除去することが治療の中心となります。同時に歯科衛生によるブラッシング指導を行い、自分でプラークコントロール(歯垢除去)できるようめざします。

- 2中度の場合
- 歯がぐらつく、歯茎から膿が出るといった症状がみられる中度の歯周病の場合、局所麻酔などを使いながらまずは歯石を徹底的に除去する治療を行います。通院回数は5~8回程度、期間も3カ月くらいかかります。

- 3重度の場合
- 重度の歯周病になると「歯槽膿漏」と呼ばれ、歯を支える歯槽骨のほとんどが溶けてしまいます。こうなると口臭も強く、硬いものが噛めない、ブラッシングの度に出血するなどの症状が見られます。この場合は歯石除去だけで改善が難しいこともあり、抜歯や外科的な治療、再生治療など保険外の治療が必要になることもあります。